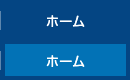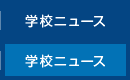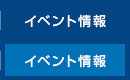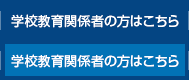小学校からはじまる日本の英語教育改革
人口減少が進み、国内の産業が頭打ちになる中で、企業のグローバル化はすでに進み始めている。もはや市場は国内のみでは立ちいかなくなり、新興国をはじめとする海外に日本企業は目を向けている。従来の輸出型企業に限った話ではない。たとえば、国内産業の典型とも言われる鉄道業界も、技術の海外輸出に活路を見いだそうとしている。生産年齢人口の減少を補うため、海外の人材を積極的に採用する動きも加速する。間違いなく国際的なコミュニケーション能力が問われる時代がやってくる。
そうした中、日本の英語教育が大幅に変わる。2018年。あと3年だ。これまで、日本の英語教育は、勉強したはずなのに話せるようにならないという批判にさらされてきた。「(こうした)反省を踏まえ、文法・単語の暗記そして訳を重視した今までの知識主体型の英語教育から、英語を使ってコミュニケーションできる力を養う英語教育にシフトしようとしています」。こう話すのはベネッセコーポレーション・教育事業サービス部の今村健吾氏だ。
■教育体系はどう変わるのか。
「まず、目玉の一つは、2018年度から、小学校英語が教科化されて成績がつくことです」(今村氏)。具体的には、小学5・6年生は英語が教科化される。授業は週3コマ程度で、こちらは算数・国語のように通知表に成績が反映される予定だ。「そして、英語活動は小3、小4で実施されます」。この英語活動は、従来の小学5・6年で導入されていたものを前倒しにしたもので、成績はつかない。授業は週1~2回を想定、英語を使ったコミュニーションの素地を養うのが目的だ。
(資料)小学英語学年早見表 ベネッセコーポレーション制作「2018年、英語教育が変わります」より引用
だが、英語学習年齢の前倒しは、改革の一部にすぎない。今村氏によれば、「大学入試自体、英語の位置づけが大きく変わります。その文脈の中で、見ていくことが重要なのです」と指摘する。
事実、中教審の大学入試改革答申には「英語は4技能(聞く・読む・話す・書く)を総合的に評価できる問題の出題や民間の資格・検定試験の活用」がうたわれている。その流れを受けて、平成26年5月に文科省から発表された平成27年度の大学入学者選抜実施要項にも、すでに「4技能」を測定できる英語検定試験の結果の活用が盛り込まれた。
■英語の外部試験はどう活用されるのか
そもそも外部試験とは英検・TOEFL・GTEC・TOEICなどの民間で行われている英語検定試験を指す。詳細は英語4技能試験情報サイト(http://4skills.eiken.or.jp/)で紹介されている。
その外部試験が大学入試とどのように関わってくるのか。「大学入試への活用の方法としては現状では、主に5種類に分類できるかと思います」と今村氏は説明する。その5種類とはこうだ。
1)書類審査型・・・様々な提出書類と合わせ、合否判定に活用
2)出願基準型・・・基準スコアを満たす者だけが出願できる。
3)試験代替型・・・英語の学科試験の代替として、外部試験のスコア―を活用する。
4)みなし得点・・・英語の学科試験は廃止せず、外部試験のスコアに応じてみなし得点を設定。みなし点が当日試験より高い場合に得点を代替する。
5)ベースアップ型・・・英語の学科試験は廃止せず、外部試験のスコアに応じて得点加算する。
たとえば、九州大・法学部は、平成27年度のAO入試で調査書、志望理由書に加え、英語能力試験のスコアを条件にした。これが書類審査型だ。みなし得点型をとる長崎大・多文化社会学部(一般入試)のケースだと、平成26年度は、外部試験のスコアを一定基準満たす受験生は、センター試験の英語を満点として取り扱った。長崎大では、平成28年度までに、外部試験の対象を拡大し、基準とするスコアも段階的に高めに設定していく方針だ。
■変わる高校入試
こうした流れは高校入試にも波及しつつある。
大阪府教委では、「実践的に使える」英語教育への転換に向けて舵を切りつつある。その施策の中核は、「読む・聞く・書く・話す」の4技能をバランスよく学習すること。平成29年度の府立高入試から、難易度が最も高い英語の学力検査問題を大きく改革することが決まった。これは、「4技能」に対する考え方を高校入学者選抜という形で具現化したものだ。大阪府教委では大学入試同様、高校入試にも外部試験との連携を視野に入れている。大阪府教委はこの施策にあわせ、グローバル・リーダーズ・ハイスクール(10校)を設置し、選抜された英語の指導のベテラン講師を配置していく予定だ。
大阪ほどではないが、全国的な傾向として公立高校の入試の英語問題自体が質的に変わりはじめている。たとえば、茨城県公立高校の入試問題では「アメリカ人の留学生とテニスする予定だったが、朝起きると雨だったという状況に対し、他の予定をメールで提案する」問題が出題された。これを英語で15語以上25語以内で英作させる内容だ。
「以前であれば、この手の問題は、文法的な瑕疵(かし)がなければ、得点がつきました。たとえば、代替案を野球にすると書いてもマルがついたわけです。ところが、最近はその問題の意図がしっかり汲まれているかまで見られます。雨が降っているわけだから、野球というのは考えにくいわけで、状況に対する適切さ まで採点基準に反映されるようになりました」と今村氏は話す。高校入試の英語がコミュニケーションにウエイトを置きはじめた好例といえる。
自由英作文の制限語数も、年々増えている。
群馬県入試でも地殻変動は起きている。「2年前の公立入試から英語は質的に変わりました」。こう話すのは県内で英語を指導する塾の講師。「長文内容を日本語に要約させるような問題、長文の一部を空欄にして、そこにあてはまる適切な内容を自ら表現する問題など表現する力がより見られるようになってきました」。この年、英語は大幅に平均点を落とした。過去11年の平均が52点に対し、41.2点。50点を超える年が多かっただけに、塾で英語を指導する講師の間では、話題になった。そして、昨年は若干平均点は盛り返したものの、出題形式は踏襲され、45点だった。「今の英語改革の流れを見れば、群馬の公立の英語も難化していくのではないか」と先の講師は分析する。
■使える英語の身につく教育へ
2018年度から実施される小学校の英語教育改革は、小学校という「局部」的な改革ではなく、大学入試、ひいては日本の教育全体が大きく変貌を遂げようとする文脈の中に位置づけられたものだ。いかに「使える英語力」を身につけられるか。その活用力にまでスポットライトがあたる。それは、教育業界のみならず、人口減少が進み、市場が縮小していく中で、産業界からの要望でもある。少なくとも、文法だけの英語の時代は終焉を迎えるのは間違いないだろう。
(編集部=峯岸 武司)
関連記事
編集部より 記事は配信日時点での情報です。