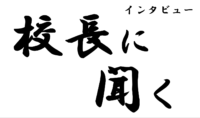【シリーズ】校長に聞く(第3回) 桐生大学附属中学校 神子澤修校長
24年4月付けで、桐生大学附属中学校(桐生市小曽根町)の校長に就任した神子澤修先生(64)に「どんな学校にしたいか」「どんな校長になりたいか」などインタビューしました。
――校長就任おめでとうございます。まずは新任校長ということで、どんな学校にしたいと考えていますか?
1901年に学園を創設された長澤幹子先生の建学の精神「社会に出て役に立つ人間の育成」が学園のよりどころですから、これを常に念頭に置いて学校運営に努めていきたいと思っています。
本校を卒業した生徒が「桐生大学附属中の生徒って良い意味で違うよね」と社会の皆さんにそういう風に思っていただける生徒を育てていきたいですね。

【写真】神子澤修校長(同校・エントランスで)
――桐生大学附属中の特色とは?
土曜日は基本的に講座という演習中心の授業があります。英語教育に力を入れているのも特色の一つだと思います。
本校には「特別進学コース」と「進学スポーツコース」の二つのコースがあります。「進学スポーツコース」にはサッカーのコースに加え、今年から軟式野球のコースが新設されました。
世間を見渡すと、少子化の流れの中で中学校の部活動が成り立ちにくい状況になっています。複数の公立中で合同チームを編成したり、部活動の地域移行が進む中で、サッカーや軟式野球が自校で一貫して取り組めるというのは大きな売りだと思っています。中高一貫なので、中学部活動終了後も空白期間がなく続けられるのも利点です。


――先生が教師をめざしたきっかけは何ですか?
正直話しますと、最初から教師を目指していたわけではないんです。私は明治大学に通っていたのですが、その当時、慶応大学の小此木啓吾先生が名付けた「モラトリアム」全盛期だったんです。(モラトリアム:若者が人生の選択をさけていつまでも可能性を保ったまま、大人になることを拒否して猶予期間にとどまる傾向)
同級生が就職活動に没頭している中、就職には興味が持てずにいたんです。自分の進路を決めかねていたその時期、たまたま本屋で見つけた「病は食から」というフレーズに触れて、漠然と栄養士という職業に興味を持ったんです。それで桐丘短期大学(当時)の入学を決めました。
――先生は富山のご出身と伺っています。またなぜ群馬の短大に進んだんですか?
たしかに群馬は縁もゆかりもない土地でした。40年前は今と違って、男性で栄養士の資格も取れる大学は数えるほどしかなかったんです。その中で地理的にも近い桐丘短大を選びました。
――で、栄養士ではなく教員になったわけですね。
桐丘短大でお世話になった指導教授に「君は栄養士と言うよりも教師が向いているんじゃないか」とアドバイスされたんです。その先生の言葉で教員の道を選びました。当時の桐丘高校(現・桐生第一高校)の調理科の教員として入職しました。家庭科の先生です。実は昨年まで桐生第一高校の教頭をしていましたが、教頭在職中も週に6時間は教壇にたっていました。
――先生のお仕事をしていて嬉しかったことや辛かったことはありますか?
この仕事は何かを作り、売る仕事ではありません。目に見えた何かがあるわけではないので、成果が分かりにくい仕事です。数年経って、卒業生が立派に社会で活躍している姿を見聞きしたときが教師冥利に尽きる瞬間ですね。オープンスクールで卒業生がお子さんを連れてきて「ウチの子どもです。またよろしくお願いします」。こういうシーンがよくあるのですが、その時は自分たちのしたことは間違っていなかったんだととても温かい気持ちになります。
反対に辛いのは即効性がないときです。教師ですから「君のやっていることはいけないことなんだ」と注意することもあります。その注意指導に対して、それをなかなか理解してもらえない時に、自らの力量のなさを痛感します。
(聞き手・峯岸武司)
関連記事
編集部より 記事は配信日時点での情報です。