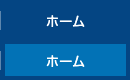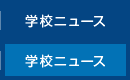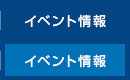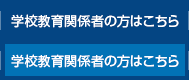【私小説】Nの青春<第2章> その1

第2章
天才とは、1%のひらめきと99%の努力である
その1
同級生のSとは浅からぬ因縁があった。
それはNの成績の低下に薄っすらと関わってはいるのだが、しかしそれは当のSには全く責任のないことで、いやむしろSはそんな同級生の内面のどうでもよいことに興味を持つような人間ではなかった。彼はNの知る限りで“天才”の一人だった。
NとSとは小学5年生の時には同じクラスに在籍していたものの、Sとの明確な記憶は6年生になる直前の春の出来事からだった。
正月のお年玉が初めて1万円の大台に乗って喜んだNは当時流行っていたボウリングゲームかレーシングカーセットを買おうと思っていた。どちらも1万円に近い金額だったのでしばらく悩んでいると、それを知ったNの祖父が唐突に尋ねてきた。
「お前の本当に欲しいものはソレか?」「もっと欲しいものは無いのか?」と。
Nはずっと本物の顕微鏡が欲しかったのだが到底1万円で買える代物ではなかったので、それを祖父に話すと
「その貯めたお年玉の1万円を全部じいちゃんに寄こせ。そうしたらじいちゃんがそれと同じ金額をお前にやろう。」と提案してきた。
Nは躊躇なくすぐにその話に乗った。だが実際には顕微鏡は3万円したので諦めようとしていると、Nの母親が「じゃあ私も」と言って残りの1万円を出してくれた。
この話を二月の始めにクラスの仲の良い同級生たちとしていた時に「本物の顕微鏡ならウチにもあるよ」と言ってきたのがSだった。話を折るとかマウントを取るとかそういうことではない、単に事実を言ってきただけだ。とにかくSはそういう人間関係や社会通念には全く頓着しない人物だったので、Nも素直に「見せて」と言って、その週の土曜日の午後にSの家を訪ねた。Nの購入予定の顕微鏡は600倍だったがSの家の物は1500倍だった。でもNの考えている(購入予定の)顕微鏡よりも小型で、それはNにとっては“おもちゃ”に近い物だった。
それから数回、早春の田起し前の乾いた田んぼで同級生たちと一緒に遊んだ。近くの麦畑からは雲雀が鳴きながら空高く舞い上がっていた。

四月、Nたちは6年生になった。5年生から6年生にかけてクラスメイトも担任も持ち上がりで全く何も変わってはいなかったが、Sだけがいなかった。5年生の終わりに転校のための「お別れ会」をしていたので別段驚くことはなかったが、驚いたのは家も遊び場も三月の時と全く変わっていなかったことだ。
「あれ?転校したんじゃなかったっけ?」
「うん。転校したよ。今はバスに乗ってN小に通っているんだ。」
「ふうん…。じゃあ、また一緒に遊べるね。」
「うん。」
それが最後の会話だった。次に言葉を交わすのはお互いがK高に入学して同じクラスになってからのことだ。
(つづく/毎週木曜掲載)
プロフィール

丹羽塾長
<現職>
桐生進学教室 塾長
<経歴>
群馬県立桐生高等学校 卒業
早稲田大学第一文学部 卒業
全国フランチャイズ学習塾 講師
都内家庭教師派遣センター 講師
首都圏個人経営総合学習塾 講師
首都圏個人経営総合学習塾 主任
首都圏大手進学塾 学年主任
都内個人経営総合学習塾 専任講師
関連記事
編集部より 記事は配信日時点での情報です。