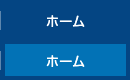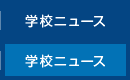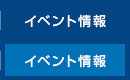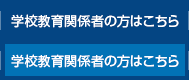【私小説】Nの青春<第3章> その3

第3章
歌は心を潤してくれる。 リリンの生み出した文化の極みだよ。
(その2を読む)
Nの同級生にT(総務委員とは別人のT)という者がいる。高校1年生の夏のテニス部の合宿の夜に、部屋で物思いに耽りながらギターを弾いていたTが突然手を止めて言った。
「うん。やっぱり僕は音大に行こう。」と。
姉の一件を経験しているので、Nは心ひそかに「いや、今からではではムリだろう」と思っていた。ところがTは翌日には退部届を提出して合宿の途中でテニス部を去ってしまった。きっと本格的な練習・音大への受験体制に入ったのだろう。もともとクラスが違っていたのでTのその後の消息はNの耳には一切入って来なかった。だがTはその後あの<東京芸術大学>を卒業して「テノール歌手」としてプロの音楽家になった。
Tの育った環境はNの育った環境と大差のないK市の周辺部だったし、Tの家もNの家と同様にその地域での旧家の一族であという点においては家族環境もおそらく大きくは異なってはいなかったはずなのだが、「音楽」に関しては<何か>が大きく違っていたのであろう。あるいはもしかしたら音楽の英才教育を受けていたのかもしれない。そんなことを<何も知らない>Nは勝手に「素人判断」をしてしまっていたワケだ。

そう、<何も知らなかった>のだ。
Nは、目先の中学の中間・期末テスト以上の勉強を<知っている>と得意がっていただけで、「学力」という当時のNの中学校ではほとんど誰も気にしていない“ちょっとカッコイイ”(と、Nが勝手に思っている程度の)勉強を<知っている>と思い込んでいただけで、しかしそれは後からよくよく考えてみれば「G県の公立高校入試」程度あるいは「G文館模擬テスト」レベルの問題がスラスラ解ける程度の「学力」だったワケで、その向こう側に『本物の学力』が聳え立って(そびえたって)いて、そしてK高程度の地方都市の高校でさえ、それを知っている多くの保護者や同級生がいて、既に準備し実践している者が多数いることなど、<何も知ってはいなかった>のだ。
「百姓の倅は百姓になれ」という時代遅れの信念を持つ祖父とそれを甘んじて受け入れて大人になった無気力な父親がいる家庭環境の中で育ったNと、一方では高度経済成長そして民主主義の発展(=ある意味での「学歴主義」)という大きな時代の変化にいち早く対応しているK高の同級生たち(およびその家族たち)の存在と。その対比と相違の狭間に立って『自分を失いかけている』ことだけは<自覚し始めた>悲しいNの姿が、そこにあった。
(つづく)
<編集部から>
来週の7月27日(木)の配信で第3章が完結し、第4章は9月から再開します。8月期間中、繁忙期になるためご了承ください。
プロフィール

丹羽塾長
<現職>
桐生進学教室 塾長
<経歴>
群馬県立桐生高等学校 卒業
早稲田大学第一文学部 卒業
全国フランチャイズ学習塾 講師
都内家庭教師派遣センター 講師
首都圏個人経営総合学習塾 講師
首都圏個人経営総合学習塾 主任
首都圏大手進学塾 学年主任
都内個人経営総合学習塾 専任講師
関連記事
編集部より 記事は配信日時点での情報です。