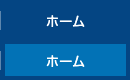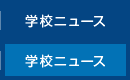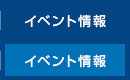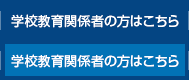【私小説】Nの青春<第4章> その3

第4章
友達は要らない。 友達を作ると人間強度が下がるから。
(その2を読む)
ところが、それはいつのことだったろう。いつものように休み時間中に窓際の真ん中あたりにある自分の座席で本を読んでいる(ふりをしている?)Nに、突然、中央の列の一番後ろに座っているIから5メートル越しの声が掛かってきた。
「なあN、お前さ、そうやってクラスの皆とわざと関わらないようにしているみたいだけど、何で?」
さらに続けた。
「一人が好きならそれはそれでいいけどさ、教室にいる時くらいはもうちょっと穏やかな態度を取ってもらえないかな。なんか俺らお前から拒否されているみたいでさ、イヤなんだよな、その態度が。なんだかんだ言ったってオレら同じクラスの同級生なんだしさ。」
『来た!“同級生”。 来た来た! おせっかいな奴』
そう思いながらもゆっくりと振り返り、でも文庫本のページは開いたままでNは答えた。
「べつに、拒否なんてしていないよ」
「人と関わるのがあまり好きじゃないだけ」
「総務の仕事はちゃんとやっているんだから、それ以外の時間は放っておいてくれないかな」

「ふーん」
……何かを考えながら、数秒後……
「ところでさ、お前、うなぎ、好きか?」
……突拍子もなくIが訊いてきた。
<うなぎ> <うな重>
Nの頭には瞬間、小学5年生の夏の思い出がよぎった。
Nの家は農家だったので、家で作るごはんのおかずの食材はほとんどが自作のものばかり(主に野菜)だった。朝の納豆や夕方の豆腐はそれぞれ家の近くまで自転車で売りに来ていた「納豆売り」や「豆腐売り」から購入したが、肉や魚は滅多なことで食卓に並ぶことがなかった。Nの家のカレーには肉の代わりに魚肉ソーゼージが、玉ねぎの代わりに長ネギが入っていた。玉ねぎは栽培していなかったからだ。そのかわりにジャガイモとニンジンだけはたっぷりと入っていた。Nは今「ベジタブルカレー」も好んで食べているが、もしあの時に「野菜カレーが食べたい」などと言い出したらいったいどんな野菜をどれくらい入れられていたか想像するだけでも恐ろしい。
Nは小学校時代、家に帰るとすぐに「おやつは?」と訊くと「トマトが冷えてるぞ」とか「キュウリに味噌を付けて食べろ」とか言われていたので、テレビのアニメやドラマで「おやつがどら焼き」とか「プリンが冷蔵庫に入っている」とかを羨ましくまるで別世界での出来事のように見ていた。
そんな折に、<土用の丑の日にうなぎを食べる>という習慣が日本にはあることを知り、Nはどうしてもそれを食べてみたくなった。何度「うな重が食べたい・食べてみたい」と母親や祖母に懇願したか知れない。家のお手伝いもそれまで以上に頑張り、学校のテストでも100点をたくさん取るようにもした。そしてついにNの祖母が「お前だけで食べてこい」と言って、うな重の値段のピッタリ1000円を渡しながら「いいかい、食べたことは家族にはゼッタイ内緒だからね」と念を押した。
Nの家から一番近い「うなぎ屋」までは3㎞ほどあったが夏の炎天下にもかかわらず何の苦もなくむしろワクワクしながら楽しく歩いて行った。開店と同時に店に入り、緊張した声で「うな重をください。」と言って席に着き、店員さんが「はい。」と言ってお冷をNのテーブルに置いて奥に入ると、その後は小学5年生の少年Nだけが店内に取り残された。ちょっと不安な気持ちで店内を見渡していたNはあることに気が付いた。「うなぎ」にはランクが付いていて、<うな重・並>が1000円、<うな重・上>は1500円、<うな重・特上>は2000円、そして<うな丼>は800円だった。

『僕はさっき<うな重>をたのんだけど、<並・上・特上>のどれとも言っていなかったな』
『もし<上>が運ばれてきたらどうしよう、1000円しか持っていないし、どうしよう』
『<うな丼>だったら200円のおつりがくるから、そっちの方がよかったかもな』
『でも、<うな重>と<うな丼>って何が違うのだろう』
『今から店員さんに聞くのもなんかイヤだし、それにもう作り始めているし、どうしたらいいだろう』
『やっぱりたのんだのは普通に考えて1000円の<並>だよな。もし違っていたらどうしよう』なんていうことを、<うなぎ>が運ばれてくるまでの約30分間ずっと考えていた。
運ばれてきた<うなぎ>はどう見ても「重箱」に入っていて、それは決して「丼ぶり」には見えなかったので、<うな丼・800円>の可能性は低いと判断せざるを得なかった。
何はともあれ<ひとくち目>をほおばると、『あぁ、これが<うなぎ>か!! 想像していたよりも美味しい♡♡♡』とうっとりした。
<ふたくち目>にも感動があった。しかし、だんだん食べ進めて行くうちに先ほどの不安が蘇って来た。
『これは確かに<うなぎ>だ』
『しかし、これは<並・上・特上>のうちのどれなんだ?』
『もしかしたらこれは<うな丼>で、この店はそれを重箱に入れて出しているのかもしれない。だったらイイな』
『もし、「1500円です」って言われたらどうしよう。「お金を家に取りに行ってきます」って言うしかないよな。でもあと500円を出してくれるかな』
『その時に誰か家の者がいたらそれも言い出せないな。内緒で来てるんだし』
『それに、初めての客の言葉を信用してくれるかな』
『これってもしかしたら「無銭飲食」って罪で逮捕されちゃうのかな』
『・・・。』『・・・?』『・・・!』『・・・?』『・・・。』・・・・。
食べ終わった頃が、この不安の頂点だった。だから結局<うなぎ>の味はほとんどと言ってよいくらい覚えていなかった。最初の<ひとくち目>の感動以外は。
(つづく)
プロフィール

丹羽塾長
<現職>
桐生進学教室 塾長
<経歴>
群馬県立桐生高等学校 卒業
早稲田大学第一文学部 卒業
全国フランチャイズ学習塾 講師
都内家庭教師派遣センター 講師
首都圏個人経営総合学習塾 講師
首都圏個人経営総合学習塾 主任
首都圏大手進学塾 学年主任
都内個人経営総合学習塾 専任講師
関連記事
編集部より 記事は配信日時点での情報です。