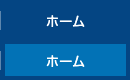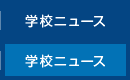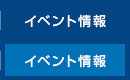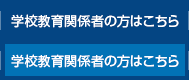【私小説】Nの青春<第1章>

第1章
生きること、それは日々を告白してゆくことだろう
その1
1970年代半ば、Nは中学3年生(受験生)だった。
成績優秀(偏差値73)だったNは第一志望校を地元のK高(地元ではこの高校のことをKコウとは呼ばずにKタカと呼んでいた)ではなく、県内のトップ校であるM高(同じくMタカと呼ぶ)にしていた。しかしNの暮らしていたG県では当時「学区制度」というものがあり、K市に住所があったNはM市にあるM高には願書すら出せない状況にあった。それでも定期的に学校で実施されていた「G文館模擬テスト」では常に第一志望校をM高にしていた。
「せめて模擬テストくらいはM高を狙っている同学年の同レベルの生徒たちと勝負がしたい」という思いからだった。
そんな折、Nの思いに応えようとNの母親は親類や知人を頼ってNの住所だけを書類上だけM市に移してNにM高を受験させてやろうと動いてくれていたのだが、明治生まれの祖父にそのことが発覚すると「ならぬ!」の一言でこの計画はお蔵入りになった。なにしろNの父も叔父も中学3年生の時にあこがれのK高を受験したいと祖父(二人にとっては父親)に願い出たところ「百姓の倅は百姓になる勉強をしろ」と有無を言わさずOMM高校(その当時は農業学校だった)を受験させられたほど、祖父は頑固な人間だった。その一方で「女は賢くなければならない」と、三人の叔母たちはみなK女を受験させられていた。(三人とも合格し成績も良かったらしいが大学には行かせてもらえなかった。)
「K高を受験させてもらえるだけでも贅沢だ」という祖父と父の言葉に、Nはしぶしぶ従わざるを得なかった。
そして翌年の4月、Nは晴れて「K高生」になった。だけではなく、やはり優秀な成績で合格していたので、Nは担任の先生からのご指名で「総務委員」を仰せつかった。総務委員とは小中学校の「学級委員」のようなもので、Nの他にもう一人、Tも仰せつかっていた。Tは学年でもトップレベルの生徒で口癖は「デスラー総統万歳!」と「理Ⅲに行く」だった。(結果は筑波の医学部に現役合格し、その後は大学教授になった、らしい)

K高の体育館はとても広かった。おそらくは中学校の体育館の2倍以上はあっただろう。それもそのはずで、全校生徒の1000人を収容できなければならず、さらには高校生用の室内競技の練習場としても使用しなければならなかったからだ。当然のことながら入学式はこの体育館で行われた。新入生代表挨拶は入試を1位で合格したM中のIが行い、新入生保護者代表挨拶は同じく2位で合格したO中のNの父親がした。主人公であるH中のNはこの時「この子たちがライバルか・・・」と意欲に燃えながら壇上からのその挨拶に聞き入っていた。
そして入学後三日目のことだったろうか、担任から「今日は応援指導があるから全員を体育館に集合させるように」との指示があった。総務委員の誘導でクラスメイトは三々五々、体育館に集まっていった。他のクラスの同級生たちもみな同様に。
新入生全員が体育館の中に入り終わった、と思われたその時、体育館の入口の重たいドアが閉められる音に後ろを振り向くと、まるでどこかの不良高校の生徒と思しき一団が手に手に木刀や竹刀を持ちながら大股で歩いて来て、体育館の中央付近にたむろしている新入生たちを等間隔で取り囲み始めた。
(つづく/毎週木曜掲載)
プロフィール

丹羽塾長
<現職>
桐生進学教室 塾長
<経歴>
群馬県立桐生高等学校 卒業
早稲田大学第一文学部 卒業
全国フランチャイズ学習塾 講師
都内家庭教師派遣センター 講師
首都圏個人経営総合学習塾 講師
首都圏個人経営総合学習塾 主任
首都圏大手進学塾 学年主任
都内個人経営総合学習塾 専任講師
関連記事
編集部より 記事は配信日時点での情報です。