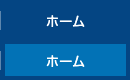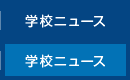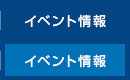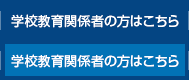【私小説】Nの青春<第2章> その2

第2章
天才とは、1%のひらめきと99%の努力である
(その1を読む)
その2
小6の四月の半ば、放課後の掃除を班のメンバーでしている時に情報通のS2が話を切り出した。
「なあ、知ってる?Sって最近一緒に遊ばなくなったよな。何でだと思う?」
「そりゃ向こうの学校で新しい友達ができたからじゃないの?」
「そうなんだけどさ。じゃあ何で転校したか知ってる?」
「知らない」
「Sの親がさ、このままH小に通っててH中に上がるとウチの子はバカになっちゃうからって、住所をおばあちゃん家に移して今からN小に転校させといたんだってさ」
「ふうん」「ってことは、Sの母ちゃんに言わせるとオレたちはみんなバカってことになるんだね」
「そうなんじゃない?」
このことを、NはK高のクラスメイトとして4年ぶりに再会したSに率直に話した。案の定Sは何の頓着も見せずに「あの時は僕もびっくりしたよ。4月からバスに乗ってN小に通えって母親から急に言われてさ。別にイヤじゃなかったからそうしただけなんだけどさ」と言った。

もしSがH中に残っていてくれたら、さもなければSや他のK高のクラスメイトのKや2年から同じクラスになるT2はじめ京大・東工大・早稲田・慶應・医学部医学科に何人もが同学年で合格している「K市教育委員会附属中学」との異名を持つN中学にN自身も転校させてもらっていたら、きっとNの人生は別のものになっていたことだろう。
思春期の男子にとってその一定の期間を過ごす “仲間” や “環境”というものがその後のその子の人生にどれだけ多くの影響を与えるかを考えたとき、Sの母親の取った行動(判断)は結果として正しかったことが証明されたと言えよう。「同級生の誰々」の問題ではなく「H町という社会環境」が才能のある子供をバカにしてしまうことを、Sの母親はちゃんと認識していたのであろう。
それに、N中学の学区内には市内でも珍しい「算数・数学の特殊な塾」が存在しており、Sをはじめ先に挙げたようなK高の成績上位生の多くがそこの塾生であった。
(つづく/毎週木曜掲載)
プロフィール

丹羽塾長
<現職>
桐生進学教室 塾長
<経歴>
群馬県立桐生高等学校 卒業
早稲田大学第一文学部 卒業
全国フランチャイズ学習塾 講師
都内家庭教師派遣センター 講師
首都圏個人経営総合学習塾 講師
首都圏個人経営総合学習塾 主任
首都圏大手進学塾 学年主任
都内個人経営総合学習塾 専任講師
関連記事
編集部より 記事は配信日時点での情報です。